こんにちは、兵庫県加古川市・播磨町で学習塾「ニードモアアカデミー」を運営している三浦です。
今回のテーマは「読解力」です!
二重否定から考える日本語の難しさ
「この水は飲んでも死なないとは限らない」
という一見複雑な文章を例に、日本語特有の読解の難しさについて掘り下げます。
この文章を分解すると:
- 主語:「この水は」
- 条件節:「飲んでも」
- 主節:「死なないとは限らない」
ここで難しいのが主節の二重否定表現です。「死なない」を言い換えると「生きる」。そして「~とは限らない」は「~ではない可能性がある」という意味になります。
つまり、この文章全体の意味は「生き延びられない可能性がある」=「死ぬ可能性がある」ということになります。
日本語には、このような二重否定や婉曲表現が日常的に使われており、「保証いたしかねます」(保証しません)のように、直接的な表現を避けるための言い回しが多く存在します。
日本語って難しい!!
日本人の読解力の現状
国際的に見た日本人の読解力
日本は世界的に見ても識字率がトップレベルであり、ひらがな・カタカナ・漢字という3種類の文字が混在する言語環境にも関わらず、識字率はほぼ100%という驚異的な水準を維持しています。
国際的な学力調査であるPISA調査においても、日本人の15歳の読解力は他国と比較して上位をキープしています。
国内での読解力低下傾向
しかし、国内の全国学力テストの結果を見ると、中学3年生の国語の点数が過去最低を記録するなど、読解力の低下傾向が見られます。特に「読む力を問う問題」や「説明文の要約」などの記述式問題の正答率が低下しているというデータがあります。
SNSと読解力の関係性
興味深いデータとして、SNSや動画視聴時間と読解力の間に相関関係が見られます。調査によると、動画視聴時間が30分未満の生徒の正答率は63.9%だったのに対し、4時間以上視聴する生徒では51.6%まで下がっていました。
この理由として考えられるのは:
- SNS特有の文章スタイル: SNSでは文章が短く簡潔で、長文をじっくり読む機会が減少
- 受動的な情報摂取: じっくり考えずに次々と情報を流し見する習慣
- 集中力や勉強時間の奪取: SNSに長時間費やすことで学習時間が減少
読解力を高めるためのアプローチ
現代社会ではSNSや動画を完全に避けることは現実的ではありません。むしろ賢く活用することで読解力を高める方法を考えるべきでしょう。
1. SNSの賢い活用法
- 有益なコンテンツを能動的に視聴する(YouTubeの教育コンテンツなど)
- 「なぜこうなるのか」と思考しながら見る習慣をつける
- 批判的読解力を養う(情報の真偽を判断する力)
- 読んだ本の内容をSNSにアウトプットする
2. 読書習慣の確立
- 興味のある分野の本から始める(ハードルを低く設定)
- 1日10分からでも継続的に読む時間を作る
- 漫画から活字本へのステップアップを意識する
- 漫画だけでは絵で理解できるため読解力向上に限界がある
- 好きな漫画のノベライズ版や映画の小説版から入るのも良い方法
3. 音読の習慣化
- 文章をそのまま正確に読む力を養う
- 特に小学生のうちは重要
- 書かれた通りに読めないと、勝手に助詞を追加・省略するなどの誤読が発生
4. 読んだ内容のアウトプット
- 本を読んだ後、内容を自分の言葉で説明する練習
- 散らばった情報を整理して要約する力を養う
- 親子のコミュニケーションとしても有効

まとめと次回予告
読解力は単に文字を読めるだけでなく、その意味を正確に理解し、処理する能力です。
現代のSNS文化の中で子どもたちの読解力を高めるためには、能動的な読書習慣と適切なアウトプット練習が重要です。
SNSや動画を単に否定するのではなく、それらを賢く活用しながら、子どもたちの読解力向上をサポートしていきましょう!!
次回も読解力についてです。(後半パート!)
「ニードモアアカデミーの読解力向上を意識した指導法」などについて触れていきます。
ニードモアアカデミーは、兵庫県加古川市・播磨町で小中高生向けの学習指導を行っています。2025年の高校入試では全員が第一志望校に合格する素晴らしい実績を残しました。新しいポッドキャスト「ニードモアの聴く塾便り」も始まりましたので、ぜひご視聴ください!!
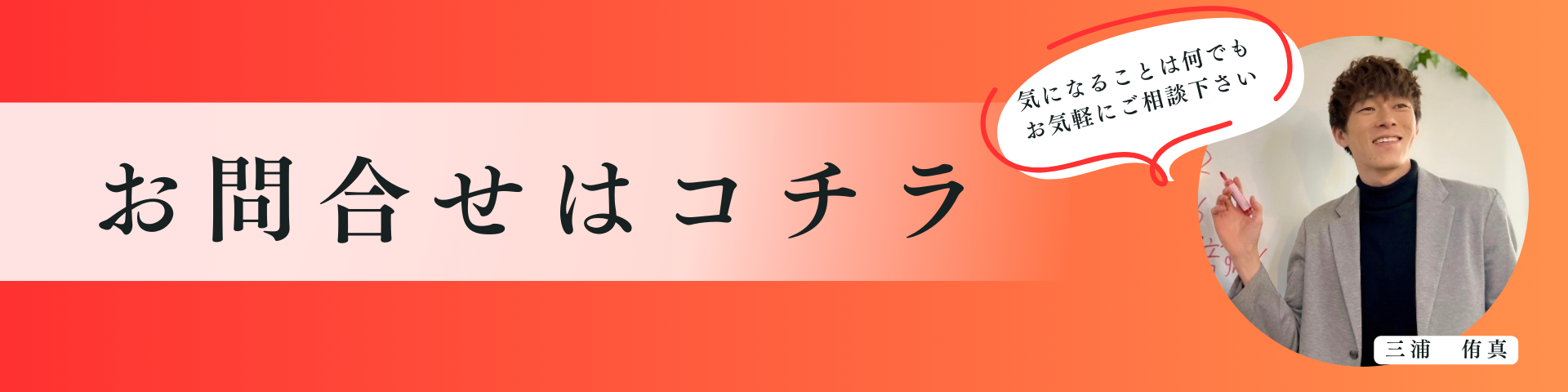

コメント